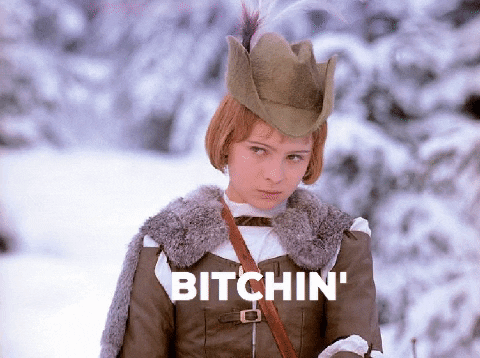シンデレラほど繰り返し語り継がれてきた童話は少ないが、チェコの『シンデレラへの3つの願い』(1973年)ほど静かに革命的な翻案作品も稀有だ。 ヴァーツラフ・ヴォルリーチェク監督、輝かしいリブシェ・シャフランコヴァ主演。この愛すべきチェコ映画は、伝統的なシンデレラ物語を覆し、ヒロインを単なる境遇の犠牲者ではなく、主体性、知性、そして遊び心のある反抗心を備えた若い女性として描いている。雪化粧した童話の舞台設定の下には、心理学、ジェンダー・アイデンティティ、そして再解釈されたセクシュアリティへの魅力的な探求が隠されており、より深く分析するにふさわしい豊かな題材となっている。

シンデレラの心理と内なる強さ
冒頭から、ポペルカは受動的な受難者ではなく、感情的に強く、精神的に機敏な若い女性として描かれている。孤児となり深い悲しみに暮れる彼女は、継母の冷酷な冷酷さとくすぶる恨みを交互に浴びせられる支配下で暮らしている。義理の妹はつまらないことで、彼女を嘲笑する。彼女たちのやり取りには、家庭内暴力や心理的ネグレクトの影が漂っている。怒鳴り合い、感情を揺さぶられ、沈黙させられる場面は、これが単なるおとぎ話のような不都合ではないことを、不安を掻き立てる。
しかし、ポペルカは壊れるどころか、ひそかにある種の回復力を身につけていく。彼女の生存は肉体的なものであると同時に、精神的なものでもある。彼女の真の味方は、権力を持つ他の人間ではなく、彼女が世話をしている動物たちと、彼女の両親を覚えていて、彼女の本当の姿を見てくれる忠実な助っ人(ウラジミール)だ。彼らはただおしゃべりな仲間ではなく、共感と記憶が生き続ける世界、愛が喪失を超えて生き続ける世界を象徴する存在なのだ。

ディズニー黄金期のロマンチックで清潔なヒロインとは異なり、シャフランコヴァのポペルカは心理的に複雑です。彼女は救済を求めることも、自らを憐れむこともありません。狩人のマントを羽織ること、謎かけをすること、王子に決闘を挑むことなど、彼女の選択は、狡猾さと勇気をもって現実と向き合う、多層的なキャラクターを反映しています。このシンデレラの心理は、現実逃避ではなく、自己決定と創造的な抵抗に根ざしています。
ジェンダー規範への挑戦
『シンデレラに3つの願い』で最も印象的なのは、伝統的なジェンダーロールの解体だろう。ポペルカは単なる受け身の王女様ではない。馬に乗り、矢を放ち、周囲の男性キャラクターを出し抜く。魔法や誘惑ではなく、技量と知性によって。彼女の女性的なアイデンティティは、男性的な行動によって損なわれることは決してない。むしろ、この映画は、強さと優しさが一人のキャラクターの中に共存できることを示唆している。
彼女と王子の関係もまた、典型的なおとぎ話の筋書きから逸脱している。王子を演じるのは、後に『パルプ・フィクション』でジョン・トラボルタの吹き替えをチェコの観客向けに華麗に演じたパベル・トラヴニーチェク。二人のロマンスは、一目惚れではなく、好奇心と互いの称賛に基づくものだ。ポペルカは美しさだけで王子に「選ばれた」わけではない。彼女は機知、自立心、そして優れた身体能力によって王子の心を掴むのだ。このように、この映画は序列や救出劇ではなく、対等な関係と遊び心のあるライバル関係に基づいたパートナーシップのモデルを提示している。
セクシュアリティとパフォーマンス
『ヴァレリーと不思議な一週間』の夢のような霞がかった物語とは対照的に、思春期のヴァレリーが欲望、恐怖、そして断片化されたセクシュアリティが織りなすシュールな世界を彷徨う『シンデレラへの三つの願い』は、より繊細で自信に満ちた女性らしさを描いています。ヴァレリーの世界は象徴と脅威に満ち溢れ、彼女のセクシュアリティは神秘的で未だ形成途上にあるものであり、好奇心に満ち、無防備で、しばしば他者に操られています。
一方、ポペルカは、厳密には子供向けのおとぎ話の登場人物ではあるものの、その体現ぶりはより成熟しているように感じられる。彼女のセクシュアリティは決して中心的なテーマではないが、彼女が世界を歩む静かな自信を無視することはできない。彼女は舞踏会にベールをかぶって現れたり、狩猟服を着て現れたり、灰にまみれて現れたりと、パフォーマンスを巧みに操っているが、それは欲望を掻き立てるためではなく、知覚を操るためだ。それは誘惑ではなく、戦略なのだ。

ヴァレリーの経験が儀式と脆弱性の体験であるのに対し、ポペルカの経験は命令の体験である。彼女は自分がどう見られているのかを自覚し、その認識を意図的に利用する。彼女が変容していく過程には、深い力を与える何かがある。理想化された王女ではなく、それぞれが自分の目的を果たす、様々なバージョンの自分へと。ヴァレリーとは異なり、彼女の体は決して妥協の余地がなく、完全に彼女のものなのだ。
この重層的なジェンダー描写は、観客のロマンスに対する認識を複雑化させる。王子が恋に落ちるのは、理想化された乙女ではなく、彼を何度も困惑させ、挑発する人物なのだ。こうして、この映画はおとぎ話のセクシュアリティを、客体化から、繋がり、好奇心、そして規範の揺らぎへと巧みに方向転換させている。
でも…あの王子様?
さて、王子様について話しましょう。
堂々とした頬骨と魅力的な戸惑いを漂わせるパーヴェル・トラヴニーチェク演じる王子は、率直に言って、歩く孔雀のようなところがある。甘やかされて育ち、虚栄心が強く、退屈に浸りきって狩りだけが唯一の趣味だ。癇癪を起こし、友達をからかい、森で自分を負かしている謎の「少年」が実は自分と同等の存在、ポペルカ自身であることに気づくのに、ひどく時間がかかる。だから、誰もが疑問に思う。なぜ彼なのか?

正反対のものが惹かれ合う、というのだろうか?カボチャではなく王子様を変身させる、つまりこの浅はかな浮気者をまともな人間に変えるというアイデアに魅了されているのだろうか?それとも、もしかしたら、ポペルカは完璧なパートナーではなく、ちょっとした楽しみを求めているのかもしれない。そもそも、彼女はかなり悲惨な家庭環境にあった。ハンサムでしつけやすい王族との気楽な恋愛こそ、まさに彼女が求めていたものだったのかもしれない。

あるいは、もっと挑発的な言い方をすれば、彼女は彼がどんな人間なのかをちゃんと知っていて、今の彼ではなく、彼女のような女性が傍らにいればどんな人間になれるかという可能性を考えて彼を選んだのかもしれません。これは、救われるべきは女性ではなく、男性であるという、古くからある紋切り型の表現をフェミニスト的に再解釈したものです。
いずれにせよ、このおとぎ話は、それ以外は完璧なスノードームに奇妙なひねりを加えている。彼女の選択には矛盾がつきものだが、おそらくそこがポイントなのだろう。愛は人間と同じように、複雑で不完全であり、時には論理では説明できない理由で選ばれることもあるのだ。

『シンデレラの3つの願い』は、その魅力だけでなく、静かに革新的であるがゆえに、今もなお愛され続けています。使い古された物語を、心理的な回復力、ジェンダーの流動性、そして心の知性を描く物語へと変貌させています。リブシェ・シャフランコヴァの忘れられない演技は、王子様に救われることなく、欠点もすべて含めて対等な人間として王子様に出会うシンデレラの姿を映し出します。この翻案は、老若男女を問わず、観客に、伝統的なおとぎ話の女性らしさという枠をはるかに超えて、成長すること、愛すること、そして所属することの意味を改めて考えさせるでしょう。優しく雪景色に包まれた『シンデレラの3つの願い』は、これまでに作られたシンデレラ物語の中でも、最も進歩的で心理的な洞察に満ちた再解釈の一つと言えるでしょう。
チェコ映画『チブンダレラへの3つの願い』のオリジナルポスター。